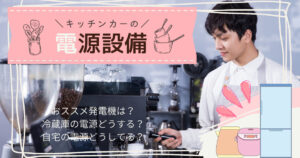キッチンカーを自作したいと考えてみたものの、どのように作ればいいのかわからずお悩みではないでしょうか。
そこでこの記事ではキッチンカーを自分でつくるための「ヒント」として、
- 軽トラックに載せる箱(架装キッチン)の作り方
- 外装・ボディをDIYで塗装する方法
- 床を自作する方法
- 軽バン・ワゴン車の後部座席|撤去と取り外し方
- キッチンカーの間仕切りを自作する方法
- 電源を確保する方法
- 換気扇を設置する方法
- シンクに水道蛇口を取付ける方法
- 給水・排水タンクを設置する方法
- 給湯器を取り付ける方法
についてご紹介していこうと思います。
ただしこの記事で解説する内容は、キッチンカーの営業許可についてある程度理解のある方でないと難しいかもしれません。
 Mint
Mint営業許可についてまだご存じないという方は先に営業許可を取得する方法を読んでいただき、中身を理解してからこの記事を読み進めてみてください。
またキッチンカーのベースになる車種ごとの大きさ・寸法、維持費や製作費用についてはこちらの記事↓を参考にしてくださいね。


それでは、早速キッチンカーを自作する方法についてみていきましょう。
キッチンカーの外枠・箱・架装キッチンをDIYで自作する


ではさっそく、キッチンカーの外枠・箱・架装をDIYで作って乗せる作業について解説したいと思います。
まずここで言う「外枠・箱・架装キッチン」というのは、上記の画像のようにトラックタイプの車の後部に造作する後付けキッチンのこと。
この部分は一般的にキッチンカーの専門業者に頼んで製作されるか、製作済みの中古キッチンカーを買うかのどちらかになります。



ですが最近ではこの画像のように、木材で造作した架装キッチンをトラックに積んで営業される方もいらっしゃるようです。
ただしこの方法、個人的にはあまりオススメできる方法ではないのかな・・・と感じています。
その理由としては、
- 走行中の安全性が担保されない
- 木材の多用でかなり重くなってしまう(かも)
- 保健所の営業許可が取れない可能性がある
の3つ。
ちょっと補足解説しておきますね。
リスクやデメリットが多いのでは・・・?


たとえば「キッチン内部」をDIYで仕上げて失敗したとしても、他人に迷惑をかけることはないでしょう。
ですが「車両の外側部分」を素人のDIYで木造で仕上げた場合、走行中に受ける風圧や振動、前後左右の揺れに十分耐えうる安全なものになるのでしょうか?
かといって過剰に丈夫な作りにしてしまうと、今度は全体の重量がどんどん重くなってしまう可能性があります。
また床や壁(側面)が木製のキッチンカーとなると、保健所の営業許可が取得できないかもしれません。



そんな考えから、あまりオススメできる方法ではないというのが私の率直な感想です。
ですがDIYで作ったものを車両に乗せること自体は法令に違反するものではありませんし、(保健所の許可が取れれば)そこまで気にすることでもないのかもしれません。。。
営業許可の実情やご自身のDIYの知識やスキルなど、総合的に考えた上で各自考えてみてみてくださいね。
架装キッチンをDIYで自作する方法
さて、架装キッチンをDIYで自作する方法として参考になるのが「軽トラモバイルハウス」です。
最近はキャンピングカーブームで、このようなモバイルハウスを製作する方が増えています。
構造としてはキッチンカーと同じですので、作ろうと思う方は参考にすると分かりやすいと思います。
ただしDIYで自作できるものとして紹介されているのは、すべて取り外し可能な架装ボックスです。
(ちなみに私の車の架装キッチンは、取り外しできないタイプです。)
近年、大阪の保健所では取り外し可能な架装キッチンが認められなくなっており、この傾向は他の保健所にも広がるかもしれません。ご注意ください。



以上、架装キッチンの作り方のご紹介でした☆
移動販売車の外装・ボディをDIYで塗装する方法
ではつぎに、キッチンカーの外装を塗装する方法をみていきましょう。
一般的に車の塗装を業者に依頼するとなると、おおよそ15万円〜20万円前後は必要になってしまいます。
ですが最近は素人でも簡単にDIY塗装できる「車専用の塗料」が販売されています。
これを使えば、2〜3万円ほどに抑えることができそうです。
↑こちらの塗料はカラー展開も豊富。
実際の使用方法も動画↓で解説されていますので、初めての方でも挑戦しやすいと思います。。
自分で塗装する際の注意点
■一度塗ってしまうと板金塗装屋さんに修理に出せなくなります。
■洗車機はご利用出来ません。出典:楽天市場
ただし商品ページの説明にあるように、一般的に塗装された車と違ってメンテナンスには少し注意が必要なようです。
その点も十分納得した上で行ってくださいね。
無塗装でも全然OK
なお、キッチンカーだからといって必ずしも塗装する必要はないと思います。



現役オーナーの中には、購入時の車体の色のままキッチンカーにされている方もたくさんいます。(真っ白のまま。真っ黒のまま・・など。)
塗装作業はキッチンカーを開業したあとからでも行なえますし、予算や状況を見ながらでも遅くないのではないでしょうか。
移動販売車・キッチンカーの床をDIYで自作する方法
つぎに「キッチンカーの床」の作り方を見ていきましょう。
キッチンカーの床面は、たいていコンパネ+フローリングマットの組み合わせで製作されます。
保健所の規定によっては、その保健所指定の素材で仕上げる必要があるかもしれません。
いずれにせよ「水拭きできる素材」を使って仕上げる必要がありますので、どんなものを使って床面を仕上げたらいいか、あらかじめ保健所に確認してください。
床作りのポイント1|コンパネは厚さのあるものを
さていろんな床材がある中から、今回はコンパネを使った床面の作り方に絞ってご紹介していきます。
コンパネを使った床面製作には、いくつかポイントがあります。
まずコンパネは、厚さ10mm以上のものを選んでおくと後々便利です。
厚みがあるとそのコンパネにビス止めできるようになりますので、あとで床面に調理台などの設備を固定できるようになります。
曲線の多い車にコンパネを設置するのは少し大変かもしれませんが、曲線に合わせてカットする方法は上記の動画↑で詳しく解説されていました。
参考にしてください。
床作りのポイント2|エンジンルームを塞がない
ポイント2つ目は、車の整備に必要なエンジンルームのコンパネをくり抜いて製作するという点です。
画像のように、車の荷室部分には車を整備するための開口部が設置されている場合があります。
この開口部を完全に塞いでしまうと、車のトラブル発生時、すぐに整備することができません。
よってこの開口部分だけはコンパネが取り外しができるようにくり抜き、コンパネの蓋を作っていつでも取り外しができる状態にする必要があるのです。
床作りのポイント3|床面の「たわみ」を取る
ポイント3つ目は「コンパネのたわみ」を出さない工夫をするという点。
コンパネを直接敷いただけでは床面がたわんだり、ずれてしまいます。
そこでコンパネの下に骨組みを敷いておき、その骨組みにコンパネを打ち付けて固定すると、丈夫な作りになるそうです。
たわみを取るならこんな方法も
コンパネのたわみやズレを防止する方法としては、コンパネ同士を互い違いに重ねて敷く方法が紹介されていました。
こちらのブログにその様子が紹介されていますので、参考にしてみてくだい。
(その際はコンパネ1枚の厚さは、10mm以下の薄いものでもいいかも。)
他にも、すのこをつなぎ合わせて骨組みにする方法も参考になりそうです。
床作りのポイント4|フローリングマットは濃い色を選ぶ


4つ目のポイントはフローリングマットの色です。
コンパネの上にフローリングマットを敷く場合、色の濃いものを選ぶと汚れが目立ちにくいのでオススメです。
(わたしはご覧のとおり薄い色のマットで製作しましたが、これだとかなり汚れが目立ってしまいすごく後悔したので・・・。)
・ワゴンの後部座席を撤去する方法


以上のポイントに注意して製作すれば、DIYでも床面製作が可能です。
ただしバンタイプの車両を選ぶ場合、もともと付いている後部座席をどうにかしなければキッチンスペースを確保することができません。
そこでDIYでキッチンカーを自作される方が最も多い「軽バン」を例に挙げて、どのような工程でキッチンスペースを確保すればいいのか、具体的な方法をご紹介しておこうと思います。



後部座席にキッチンスペースを確保する方法は2つあります。
キッチンスペースを作る方法2つ
①後部座席を折りたたみ、フルフラットにする
1つ目の方法としては、軽バン後部座席を完全に折りたたみ、フルフラットにする方法です。
これだとキッチンカーとして作業しやすい反面、床面から天井までの空間は若干狭くなってしまいます。
女性オーナーなら無理なく作業できるかもしれませんが、大柄な男性の場合はこのスペースの中で動くには狭すぎるかもしれません。
身長によっても違いますので、ご自身で確かめていただくしかありませんね。
②後部座席を撤去する
2つ目の方法としては、軽バン後部座席を完全に撤去する方法です。
これによって生まれるスペースは、たったの20cm程度(高さ)。
ですがこの20cmの高さによって空間が広がり動きやすくなることから、多くの方が撤去する方を選ばれるようです。
ただキッチン部分に段差ができてしまうのがデメリットですね。
後部座席を撤去・取り外す方法と手順
後部座席の具体的な撤去方法は、上記の動画で詳しく解説されていましたのでご覧ください。
ところで座席を撤去するという場合、構造変更申請によって車検の記載事項を変更する必要もでてきます。
この点について、さらに解説を進めていきます。
構造変更の方法と申請のタイミング
後部座席を撤去するということは(軽バンの場合)乗車定員が4人から2人へ変更になるため、構造変更の届け出をしなくてはなりません。
この届出をすることにより、「二人乗りの車」として正式に車検証に明記されることになるわけですが、同時に車検を受け直す必要も出てきます。
よってタイミングとしては、できるだけ車検切れ間近のタイミングで構造変更を兼ねた車検を受けるように調整されるといいでしょう。
車のナンバー(用途)はどうなる?
なお、もともと4ナンバーの貨物車である「軽バン」を構造変更した場合は、
- 乗車定員が4人から2人へ
- 最大積載量が100Kgから200Kgへ
と変更になるだけです。ナンバー自体は4ナンバーのまま変わりません。
いっぽうもともと5ナンバーの乗用車である「軽ワゴン」を上記と同じ条件で構造変更すると、自動的に貨物車扱いとなり4ナンバーに変わることになりますね。
車検はどうなる?
構造変更後の車検についてですが、(軽車両の場合)いづれにせよ4ナンバーになるので車検は2年毎でOK。
ただしキッチン内部の調理台やシンクはすべて撤去し、空っぽの状態で車検に出してくださいね。



構造変更申請の手続きと手数料について
さて構造変更に必要な申請手続きですが、こちらは少々複雑そうですね。
もしも自分で行いたいという方は、外部サイト「はじめての構造変更申請」を参考に手続きしましょう。
こちらのサイト↑を見る限り、素人が構造変更申請を行うのはむずかしそうな気もします。
手続きに自信がない方は、車を購入するまえに構造変更を代行してくれる車屋さんを前もって確保しておいたほうがいいかもしれません。
このような構造変更は、普通の車屋さんだと拒否されることが多いかもしれませんからね・・・。



構造変更の裏ワザ?
前述の通り、構造変更の手続きを素人が行うのは難しい場合出てくるでしょう。
そんな中ネットを見る限りでは、構造変更の届けを出さずに後部座席を撤去している人も多くいるように見受けられました。
そのような方は、
- 後部座席の部分に人を乗せない(保険が下りないため)
- 車検のたびに後部座席を取り付けて車検を受ける
の2点を承知の上で行っているようですので、一応書き添えておきます。
(構造申請を行えば、車検の場合でも後部座席を取り付ける必要はありません。)



以上、後部座席にキッチンスペースを作る方法のご紹介でした☆
キッチンカーの間仕切りをDIYで自作する方法
次にキッチンカーの間仕切り製作のご紹介です。
ここで言う「間仕切り」というのは、運転席とキッチン部分を仕切る仕切り板のこと。
これは取り付け義務のある保健所とない保健所がありますので、あらかじめ確認が必要です。
軽トラックや大型トラック、クイックデリバリーなど、もとも運転席との仕切りがあるタイプの車両は間仕切りは不要です。
間仕切りを作るときのポイント
間仕切りを作るときのポイントは下記のとおり。
- ある程度硬い素材を使用すること
- 防水加工されていること(ビニールシートなどはNG)
- 取り外せないように車体や床にしっかり取り付けること
- 大きな隙間がないこと
- 後方が確認できるよう「窓」を設置すること
- 運転席には安全に運転できるスペースを作っておくこと
間仕切りを設置することで運転席は後方に動かせなくなってしまいますので、取り付ける前にかならず運転席の位置やリクライニングの角度を自分に合わせておきましょう。
その上で間仕切り位置を決めると失敗なく設置できますね。
素材に指定がない場合は、厚さの薄いベニヤ板を2〜3枚つなぎ合わせて製作し、表面にフローリング材のようなもの(←保健所に要確認)を貼るといいでしょう。
間仕切りに取り付ける「窓」について
間仕切りには窓を設けましょう。これがないと運転中、後方確認できません。
窓にはこのようなアクリル板↑がオススメです。
間仕切りの隙間対策
また間仕切りの板の外周(断端)には、「トリム」と呼ばれるクッション材を巻きつけておきます。
間仕切りを設置しても、大きな隙間が空いたままでは保健所から作り直しを指摘される可能性があります。
トリムをつけることで隙間なく間仕切りを設置できますし、見た目もキレイに仕上がります。
トリムの幅もいろいろありますので、間仕切りの板の厚みに合わせて選んでください。
間仕切りを固定する方法
pinterest前述のとおり、キッチンカーの間仕切りはしっかりと留め付ける必要があります。
間仕切りの底面はひとまず、床のコンパネにL字金具を使ってビス止めすればOK。
天井部分は車体に直接留め付けるしかないかもしれません。
車体の金属部分にもビスで穴を開けることはできますが、オモテに貫通しないよう注意が必要ですね。
車体の金属部分にネジ止めする場合はこちらのネジ↓が便利です。
金属と木材をネジ止めするときの専用ネジなので、金属でも穴を開けられます。
以上、間仕切り設置についてのご紹介でした。
移動販売車・キッチンカーに電源を設置する方法
さてつぎにキッチンカーの「電源」についてですが、じつはキッチンカーの電源設備の取り付け方法はすでにこちらの記事↓で解説済みです。


ここから先ご紹介する設備の中には電源が必要になるものもいくつかありますが、上記の記事を参考に、なんらかの方法で電源を確保するようにしてください。
(ここからは電源を確保できていると仮定した上で説明していきます。ご承知おきください。)
移動販売車・キッチンカーに換気扇を設置する方法
まず、キッチンカーには換気扇の設置を求められる場合があります。
設置が義務付けられている場合とそうでない場合があり、保健所によって対応は分かれます。
設置する場合は設置場所について規定があるかどうか、また換気扇の大きさに指定はないかどうか合わせてご確認ください。
取り付け方
換気扇はキッチンカー側面の金属部分に、グラインダーなどで穴をあけて設置されることがほとんどです。
木製の壁や金属部分など、土台となる部分に開口部を設けることさえできれば、そこにネジ止めするだけで簡単に設置できます。
取り付ける換気扇は家庭用の一般的なもので大丈夫です。
雨で濡れるのを防ぐためには、屋外用換気扇フードの取り付けも必要です。
なお開口部の設置が難しい場合には、下記のような「窓用換気扇」を使うという選択肢もあります。
高さ調整が可能で、好みの場所にこの換気扇を挟んで固定するタイプの換気扇なので手軽に設置できますね。
ただしこの換気扇で許可されるかどうかは、事前に保健所にご確認ください。
キッチンカーの調理台をつくる方法
つぎにキッチンカーの調理台を自作する方法のご紹介です。
どんなものを使って製作すればいいのか分からないという方も多いと思うので、使えそうな資材をいくつかご紹介しておきますね。
(ただしご紹介する素材が保健所で許可されるかどうか、各自確認してから使うようにしましょう。)
調理台の製作にオススメの素材①|パイン集成材
まずこちらは、もっとも手軽に購入できる「パイン集成材」↓。
表面に撥水加工が施された状態で販売されていて、既存のキッチンカーにも多く採用されている安心の木材です。
調理台の製作にオススメの素材②|カラー化粧板
防水加工済みの木材としてもう一つ、「カラー化粧板」を使うという方法もあります。
こちらも表面に加工が施されていて、保健所に認められる可能性が高いのでおすすめです。
調理台の製作にオススメの素材③|撥水セラミック塗料
次にご紹介するのは木材に塗るコーティング剤。
アク止め液を塗ったあとに撥水セラミック塗料を塗ることで、木材全体に防水加工が施せるというものです。
使い方は【動画】撥水セラミック塗料の使い方を参考にしていただき、保健所の許可を得られる方は使用を検討してみてください。
調理台の製作にオススメの素材④|クッションフロアー
また防水加工が施された壁紙シートや、クッションフロアーも許可される場合があります。
木材の上から貼るだけで簡単に仕上がり、オシャレに仕上がりそうですね。
【サイト】クッションフロアを使ったキッチンカー製作のなかで、製作の様子が丁寧に解説されていますのでぜひ参考にしてみてください。
キッチンカーのシンクをつくる方法
シンクの大きさと個数、材質を確認すること!
つぎにキッチンカーのシンクをつくる方法について解説していきます。
シンクで注意すべきポイントは、シンクの大きさと個数、そして材質です。
シンクの大きさは首都圏ほど条件が厳しく、長さ・奥行き・深さに至るまで、保健所で指定されている場合があります。
「何センチ以上」と明確に規定されてるところもありますし、「肘が入るくらいの大きさ」などと抽象的な表現の場合もあります。



材質としてはステンレスシンクなら間違いなく許可されますが、シンクの数も2個・3個と保健所によってまちまちです。
作り直しの必要がないように、十分確認のうえで製作する必要がありますね。
キッチンカーで使えるオススメのシンク・排水ホース・共栓
ではここで、キッチンカーで使えるオススメのシンクをご紹介しておきたいと思います。
まずは首都圏の保健所でも許可されそうな、大型のシンクをいくつかピックアップしてみました。
そもそもシンクは高価なものが多いので、排水ホース+共栓と合わせて1万円程度であれば安いほうだと思います。
また2個以上のシンクが必要な方で大きさに決まりがないなら、このような↑二槽シンクを選ぶと省スペースで自作できますね。
更にこちら↑は、多くのキッチンカーに設置されている小型タイプのシンク。
(保健所で許可されるなら)このような小型のシンクがもっとも省スペースでオススメですよ。
保健所の指定サイズにピッタリ合うものは存在しないのですが、少ないシンクの種類からできるだけ近い大きさのものを選んで購入してみてください。
排水ホースと共栓
排水ホースと共栓はこちらを参考に選びましょう。
キッチンカーには不向きなシンク
逆にキッチンカーのシンクをDIYで自作する場合、丸型のシンク↓はあまりオススメできません。
- シンクを埋め込むために円形の穴が必要となり、カットしづらい
- 円形よりも四角形のほうが明らかに実用的
- 保健所によっては円形シンクが許可されない場合もある
という3つの理由から、わざわざ円形のシンクを選ぶ理由がないのではと思われます。
その点も参考に選んでみてください。
キッチンカーのシンクは調理台として製作すること
またキッチンカーのシンクの上は調理台として使うことを前提に製作しておくことも重要です。
実際のところ、キッチンカーの営業中にシンクを使うことは少ないと思われます。
その代わり、狭いキッチンカーの中ではシンクの上が貴重な調理スペースとなりますので、シンク=調理台として使うことを前提にした作りにしておきましょう。
シンクを埋め込み、蓋を設置する方法
ではここで、シンクを埋め込み、蓋を付けて調理台として使えるようにする方法をご紹介します。
まず「トリマー」という工具を使い、木材にシンクを埋めるためのくぼみを作ってください。
ストレートビットと呼ばれる刃先を装着すれば、木材に一定の深さの溝を彫ることができます。
具体的な作り方は【サイト】トリマーを使った埋め込みシンクの作り方や、【サイト】キッチンカーのシンク製作で詳しく紹介されていて、とてもわかり易いので是非参考にしてみてください。
キッチンカーのシンクに水道蛇口を取付ける方法
蛇口の数と取付け方を確認!
つぎに、シンクに取り付ける方法について解説していきます。
蛇口は一つのシンクに対して、一個づつ設置するのが基本。シンクが2箇所であれば、蛇口も2個必要だということですね。



とくに出店地域が広範囲におよぶ方は、一つづつ蛇口を設置しておくのが無難だと思います。
シンクの水道は電動ポンプを使った汲み上げ式がおすすめ
シンクに設置する水道を考える際、給水タンクのコックから直接水を出せばいいのでは?とお考えの方もいるかもしれません。
確かに、一部の地域ではこの方法で許可される場合もあります。
ですが多くの保健所では「電動ポンプ式」で汲み上げた水が蛇口から出ないと許可されません。
よって、給水タンクの水栓コックとは別に蛇口を設置するしかないのが実情です。
あなたの保健所がどのタイプに該当するか、前もって確認しておきましょう。
キッチンカーの水道にオススメの蛇口
キッチンカーのシンクに取り付けるなら、断然折りたたみ式の蛇口をオススメします。
シンクのなかで蛇口を折り畳むことができれば、調理台の上はさらに有効活用できるからです。
上記商品の解説は、下記の通り。
ハンドル部分にスイッチが内蔵されたフォーセット(蛇口)です。
ハンドルを操作することで接続した水ポンプを連動させご家庭の蛇口と同じ感覚で使用できます。
ノズル部分は根本から前後360度、ノズル部の色が変わる所から左右360度回転します。商品当該ページより抜粋
取り付けの際は「ステンレスホールソー」を使って電動ドリルでシンクに穴を開け、そこに蛇口を取り付けてください。
なお、この蛇口を水道として使うためには電動ポンプ↓が必要です。
このような設置方法にできないかどうか、ひとまず保健所に確認してみましょう。
そのうえで【動画】電動ポンプを使った水道システムの作り方を参考に、水道設備を作ってみてください。
キッチンカーで使えるその他の蛇口
しかし折りたたみ式の蛇口で許可されない場合は、普通の蛇口を取り付けるしかありません。
普通の蛇口でも電動ポンプを使って水を汲み上げることはできますので、【動画】電動ポンプを使った水道システムの作り方を参考に設置してください。



ここではひとまず安価な蛇口を2つご紹介しておきますので参考にしてください。
電源を確保できない場合の水道設備の「裏ワザ」
「電動ポンプ式の水道をもっと簡単に取り付けたい。」という場合には、下記のようなポータブル式の水道を検討してみてもいいかもしれません。
リチウムバッテリー内蔵で、付属のUSBケーブルで充電すれば電源のない場所でも使用でき、フル充電すれば約2.5時間使用可能。商品当該ページより抜粋
充電式なので、(保健所に許可されたら)気軽に水道を設置することができますね。
気になる方は保健所にご確認のうえ、【動画】ポータブル水道の設置と使用感を参考に、購入を検討してみてください。
キッチンカーに給水・排水タンクを設置する方法
キッチンカーに搭載する給水タンクの注意点
次に給水・排水タンクの解説に移ります。
キッチンカーには、手洗いや食器洗い用として使うための水を搭載しなくてはいけません。



ですが搭載する水の量は保健所によって規定が異なりますし、取り扱うメニューによっても変わることがあるので確認が必要です。
少ないものだと20L、多いものでは200L分のタンクを用意しなければならないこともありますが、キッチンカーでは20Lタンクを搭載されることがほとんど。
20Lを超える場合は、20Lタンクを複数搭載することになりますね。
キッチンカーにおすすめの給水タンク
給水タンクはホームセンターで販売されているアウトドア用のもので十分ですが、複数個設置する場合は下記のようなスリムなタイプのものを選んだほうが省スペースで済むのでおすすめです。
また複数個搭載する場合は荷締めベルトで、タンク同士をまとめて固定する必要があるかもしれません。
そこも保健所に確認しましょう。
タンクを連結して大容量タンクをつくる方法
pinterestなお20Lを超える給水タンクが必要な場合、保健所によってはタンク同士をパイプで連結させて「大容量タンク」として使えるよう改造を求められる場合もあります。
タンク連結に必要な部品は、タンク連結キット販売サイトで購入できますのでご確認ください。
購入できない場合は、ご自身で塩ビパイプを使って組み立てるしかないでしょう。
その際は【サイト】塩ビパイプの組み立て方や、【サイト】タンクに穴を開けて塩ビパイプを取り付ける方法を参考にしながら作ってみてください。
キッチンカーにおすすめの排水タンク
さらに使用した水を貯めるタンクとして、給水タンクと同じ容量の「排水タンク」を設置する必要があります。
排水タンクの選び方や連結方法は給水タンクと同じです。
ただ大容量の排水タンクに限り、「衣装ケース」で代用OKとされる保健所もあるようです。
【サイト】衣装ケースで代用する方法について参考にしつつ、実際の製作は必ず保健所の許可を得てから製作してください。
また20L程度の排水タンクであれば、このような折りたたみ式のポリタンクだと扱いが楽に行なえるのでオススメです。
こちらも保健所の許可を得た上で、購入を検討してみてください。
キッチンカーに給湯器を取り付ける方法
pinterestつぎに給湯器についての解説に移ります。
給湯器の取り付けを許可条件としているのは全国的にも一部地域だけですので、それほど必要とされないかもしれませんね。
給湯器は、熱湯消毒に必要な60度以上のお湯の確保が目的とされますので、必要な場合は必ず取り付けましょう。
実際の取り付けは【動画】ガス給湯器交換の手順や【動画】電気温水器の設置を参照してください。
ただしキッチンカーの場合は水道システムとの組み合わせが必要になります。
また、本来ガス機器の取り付けは有資格者でなければやってはいけない決まりになっているようです。



危険を伴う作業ですので、できれば取り付けだけをガス屋さんにお願いするなど安全な方法を考えたほうが良さそうです。
さいごに|中古キッチンカーを上手に活用
以上、キッチンカーをDIYで自作する方法について解説してきました。
ここまでご覧いただいて分かる通り、初めて製作するキッチンカーをDIYで仕上げるとなるとかなり大変な作業となります。
DIYの知識や経験がなければ、仕上げることが難しい部分もあるでしょう。


そこでオススメしたいのは、Goonetなどの中古車市場で中古キッチンカーを購入するという方法。
中古キッチンカーなら内装設備の大半がすでに完成しているものがほとんどなので、簡単なDIYでカスタマイズする程度で仕上がるはずです。



今は中古車市場でもたくさんのキッチンカーが販売されていて、
そのなかで程度のいいものを探すというのも、かしこい方法かもしれません。
そんなことも参考にしつつ、納得のいくキッチンカーづくりにチャレンジしてみてくださいね!
それではまた☆