この記事では「キッチンカーでしっかりと儲けを出したい!」とお考えの方向けに、
- キッチンカーで儲けを出すための5つのコツ
- キッチンカーで(原価率が低い)儲かるメニューTOP10
について解説していきたいと思います。
なお、儲けを出すための5つのコツとしては下記の通りです。
- 日々の販売記録を残すこと
- 販売収支から儲からない原因を突き止める
- 安売りをしないこと
- 食材の廃棄ロスを出さない工夫をする
- 平日のランチ営業や事前注文を取り入れる
この5つの中身についても具体的に解説しつつ、「キッチンカーの儲け」についてとことん解説していきたいと思いますのでぜひ最後まで読み込んでみてくださいね。
なお「キッチンカーで得られる収入」については、下記の記事で数字をもとに詳しく解説しています。
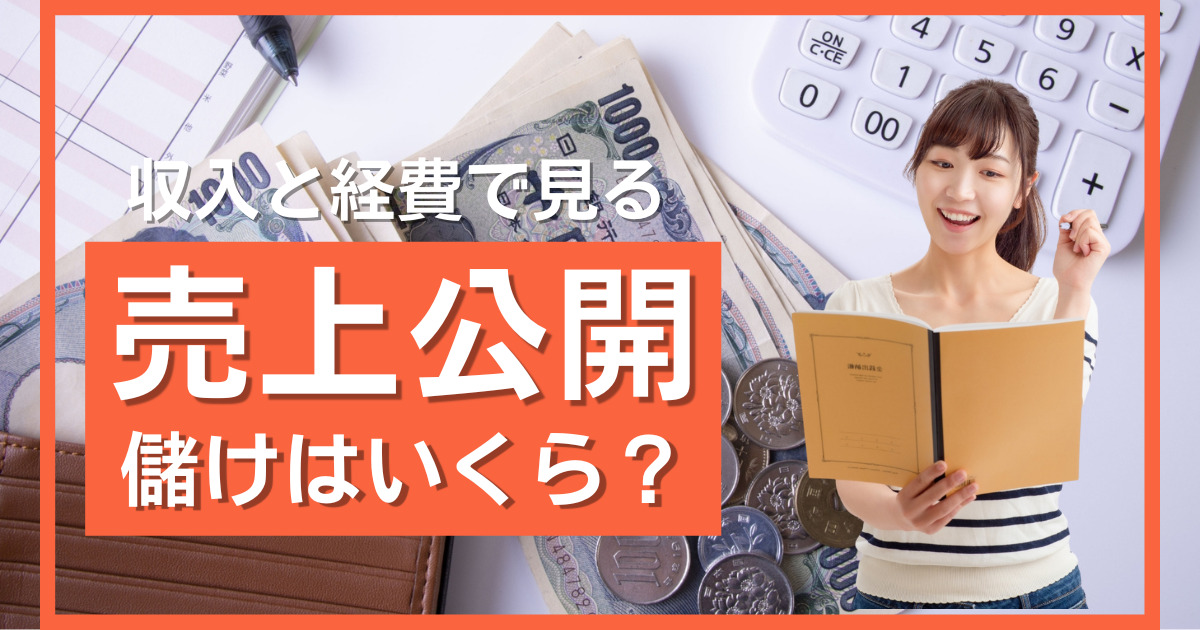
京都の過疎化が進む田舎で、わたしがクレープの移動販売によってどの程度の収入が得られたのか。
2018年の記録をもとに赤裸々に公開していますので、気になる方は参考に読んでみてくださいね☆
それでは順に解説していきます。
日商100万円?!キッチンカーで「大儲け」のカラクリ

儲けを出す5つのコツについて解説する前に、「キッチンカーで人生一発逆転大儲け!」のカラクリについて触れておこうと思います 笑)
キッチンカーオーナーのごく一部の方は、日商で100万円を超える売上を出して大成功されている方もいらっしゃるのをご存知でしょうか?
こういった方たちが大きな儲けを生み出せる理由・・・、それは「大型のイベント出店」に特化した販売形式をとっているからなのです。
「キッチンカーのイベント出店」が桁違いの儲けにつながる

キッチンカーの出店場所の記事でも解説しているとおり、キッチンカーにとってイベント出店というのは売上の大半を占めるくらい、大きな収入源となってきました。
イベントは毎年同じ時期に定期開催されるものが多く、古くからそのイベントに出店しているオーナーは毎年のように出店するのが通例です。
キッチンカーで大きな儲けを出している方というのは、そんな好条件の現場をいくつも抱えており、
- 大規模イベントに複数のキッチンカーをレンタルして出店
- スタッフはバイトを複数人雇ってとにかく大量販売
という戦法で多くの儲けを出すことができるというわけですね。
これからはイベント出店の大量販売は難しいかも・・・

こうして経費を最小限に抑えつつ、大量販売によって1日で多額の儲けを出しているオーナーさんも実際にいらっしゃいます。
ですがこのような儲け方ができるのは「キッチンカーの開業先行者」だけ。
わたしを含め、これから開業される後発組が同じように大儲けできるかというと、まず無理だと思います。
理由としては、
- コロナにより、大型イベントの開催自体が自粛され続けているため。
- 大型のイベントは人脈やコネの影響がかなり強い現場であり、出店すること自体むずかしい。
の2つです。さらに、
- 大型イベントに出店できるだけの信頼と商品力
- 大量販売に耐えうる調理機材と人材確保の力
- 人脈
など、総合的な販売力を持っている方でなければこのような儲けを出すことはできないでしょう。
よってこれから開業するのであれば、もっと地道なやり方で儲けを出していくのが現実的だと思います。
 Mint
Mintキッチンカーで儲けを出すための5つのコツ
さて、少し話がそれましたが本題にもどりましょう。
冒頭ご紹介していた「キッチンカーの儲けを出す5つのコツ」は下記の通りでした。
- 日々の販売記録を残すこと
- 販売収支から儲からない原因を突き止める
- ムダに安売りをしないこと
- 食材の廃棄ロスを出さない工夫をする
- 平日のランチ営業や事前注文を取り入れる
イベント出店での大量販売が狙えないのだとしたら、今後のキッチンカー営業では地道に日々の出店をこなしていくしかありません。
これから開業される方にはこの5つのポイントを少しでも参考にしていただき、しっかり儲けが出るキッチンカー開業を目指してほしいと思います。
それではひとつづつ中身をみていきましょう。
ポイント①|日々の販売記録を残すこと



わたしがクレープの移動販売を始めた当初は、出店の詳細な記録をまったく残していませんでした。
(ここでいう販売の記録というのは主に客層や売れたメニューの記録のことです。)
販売のことだけでいっぱいいっぱいだったということに加え、各現場ごとの客層の違いをそれほど重視していなかったことが原因です。
販売記録がないことで起こった問題とは?


開業当時の出店場所は、年に1〜2回開催されるようなイベント出店ばかりでした。
にもかかわらず記録を残していなかったため、
- 売行きを多く見積もり過ぎてしまい、大量の売れ残りが発生する
- 売行きを小さく見積もりすぎてしまい、早々に完売してしまって売上を逃す
- 客層に合わせたメニュー設定ができず、「ウケないメニュー」だけが大量に売れ残る
など、前年の教訓をまったく生かせていないことで「売行きを見誤る」という事態が、度々発生するようになりました。



イベント出店では大量販売を前提に仕込みをしますので、販売食数を見誤った時の損失はとても大きくなってしまいます。
出店場所が変わることで「客層」も変わってしまう
キッチンカーの販売では、固定店舗と違って日々いろんな場所で販売することになります。
出店先ごとに年齢や性別の割合が違うので、結果として商品の売行きが少しづつ違ったものになることを忘れてはなりません。
- 食の好み・関心
- 商品購入に使える予算
- 生活スタイル
- 行動パターン
などは、客層によって大きく変わるのです。
この事に気づいて以降、わたしは売れた数や金額と合わせて「客層の記録」も残すようになりました。
これにより売行き予測がかなり正確にできるようになり、しっかりと利益が残るようになりますので必ずやっておきましょう。
的確な「販売設定」のために必要な記録事項
販売記録の具体的な中身としては、
- 天候・気温
- 売上金額
- メニューごとのおおよその売れ行き
- 客層(年齢や性別)
- 完売した時間
- 用意した食数と、売れ残った食数
の6つです。
この記録をもとに次回出店の際の販売数を決定していくことができます。
参考にしてみてください。
レジは必ずしも使う必要はありません


補足ですが、私のクレープの移動販売ではレジは使用していません。
レジを使用することで記録は細かく残りますが、
- 調理販売スピードが相当落ちる
- 狭いスペースにレジを置くことで、調理スペースがさらに狭くなる
という、2つのデメリットが発生するからです。
レジがなくても、売上は計算すれば分かりますし、
- どんな商品が売れたのか
⇒手元に残っている食材を見れば大体わかります。 - どの時間帯に売れたのか
⇒時計見たら分かります。 - どんな客層に売れたのか
⇒その日のお客さんの年齢層や性別くらい覚えられます。 - どのくらい販売できたのか
⇒クレープの包装紙が何枚減ったか、数えれば分かります。
などは慣れてくると分かるようになり、大まかな記録を残すことで十分対応できていますので、今後もレジは使いません。



今はスマホやタブレットをレジとして使用できるサービス(有料)もあり、便利になっています。
開業して必要だと思われたときに購入をご検討ください。
ポイント②|販売収支から儲からない原因を突き止める



日々の販売記録と同様にもう一つ、必ず記録を取らないといけないものがあります。
それは販売収支の記録です。
収支がどんぶり勘定になると、自分の店の課題が明確になりません。
売上・原価・経費の3つについては、少なくとも一ヶ月ごとに振り返りをしておきましょう。
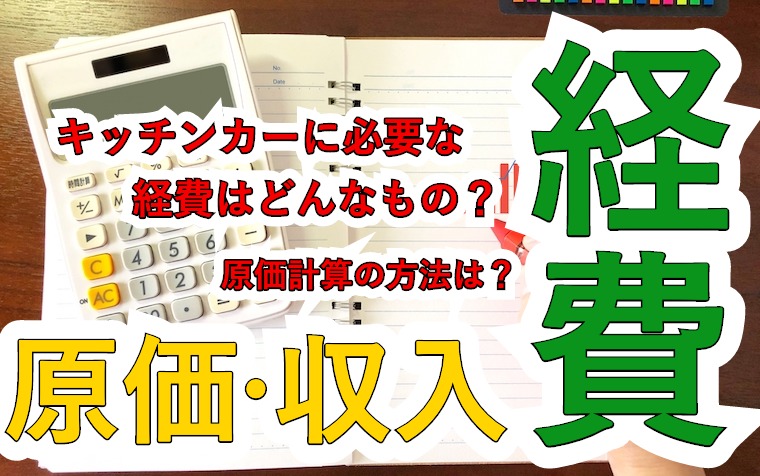
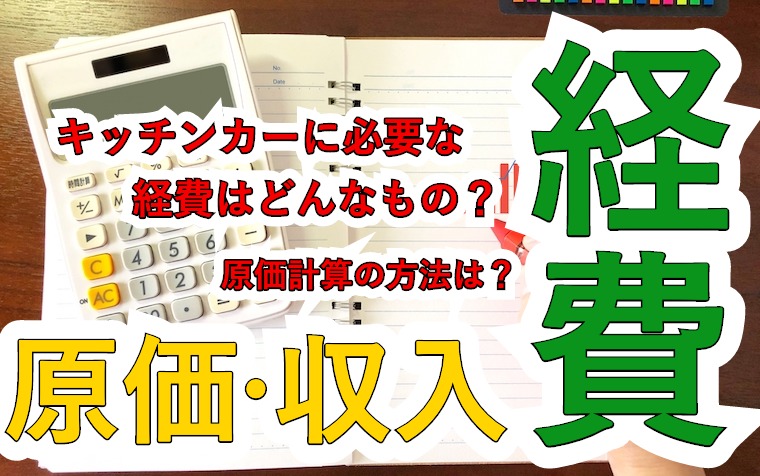
キッチンカーにおける原価や必要経費についてはこちらの記事↑でまとめていますので参考になさってください。
経営を数字で把握することで、具体的な改善策が見えてくる


一つ一つのクレープメニューの原価は30%以下に設定していました。
なのに最終的に34.02%の原価率になっているということは、相当な食材のロスが発生していたことが考えられます。
このように具体的な数字で状況を把握し、改善すべきポイントを見つけ出せるようになった結果、2018年には原価率25.71%にまで下げることに成功しました。


販売収支(の数字)は、あなたのお店のようすを正確に映し出してくれる鏡となります。
こまめに状況をチェックして、上手くいっているところ・そうでないところを販売収支から学び取るようにしましょう。
ポイント③|安売りをしないこと



クレープの販売を始めた当初、価格設定の基準がよく分からなかった私はクレープを1個300円~350円程度で販売していました。
当時は買ってもらえることに満足してしまって、どれだけ利益が残るかということを十分考えられていなかったのです。
利益を残すことを重視するようになってからは「価格改定でお客さんが離れても仕方がない」と割り切って、一気に価格を改定。
これにより、しっかりと利益へとつながっていきました。
安さで勝負してると他の解決方法を見いだせないかも?!


移動販売のベテランオーナーさんの中には、極端に安く販売されている方もいらっしゃいます。
- 安い値段じゃないと、子供が買いに来れないからかわいそう。
- これ以上値段を上げると、売れなくなるから値上げはしない。
など、儲けよりも優先したものがあるのであれば、それは個人の自由です。
ですがしっかり儲けを出していきたいなら、価格設定はしっかり行うべきだと思います。
また高く売るための努力をしたことがない方は、値段を安くすることでしか経営を改善できなくなってしまうので問題です。
高い値段でもお客さんは納得すれば買ってくれますし、喜んでくださいますし、また買いたいと思ってくださいます。
大事なのでもう一度言います。
利益を残したいと思うのなら、安売りは禁物です!
安売りで得られるものは何もありません。高くても買いたいと思ってもらえるような販売を目指しましょう。
ポイント④|食材の廃棄ロスを出さない工夫をする



食材の廃棄ロスをおさえ、原価率をできるだけ低く抑えることも儲けを出すために重要なポイントとなります。
原価率を下げるポイントとして、
- メニューすべてに原価の設定を行っておくこと
- 正確な売行き予測で、食材の廃棄ロスを最小限に抑える
- 売れない商品を排除する
の3つを意識した販売を心がけましょう。
「売れない商品」は思い切ってメニューから外す決断も必要
3つ目の「売れない商品を排除する」についてですが、たとえばクレープの場合は何種類もクレープメニューを用意するため、なかには売れにくいメニューがでてきます。


例えばサラダ系のメニュー。
たくさんあるクレープメニューの中で、サラダクレープってどのくらい売れると思われますか?
実はサラダクレープって全体のわずか10%程度しか売れません。
例えば平日の出店でトータル50食の販売を見込んだとしても、サラダクレープはそのうちの10%である5食しか売れないってことです。
これは計算上の話なので、実際には2食しか売れないこともありますし、1食しか売れなかったこともありました。
このように、売れにくいメニューを販売し続けることは売れ残りのリスクを常に抱えることになってしまいます。
さらに食材が残るということは、その食材の仕込みにかけた「あなたの時間」も無駄になってしまうという点も問題です。
思い切ってメニューから排除し、本当に売れるメニューだけをコンスタントに売り捌いていくことは、原価率を抑えるという意味では非常な有効な手立てだといえます。
ポイント⑤|平日のランチ営業や事前注文を取り入れる



前述の通り、2020年以降は残念ながらコロナによってイベント自粛が続くことになるでしょう。
イベント出店での大量販売はもう望めないと考えて、平日の出店重視で出店先を探すのが大切だと思います。
そこでオススメしたいのが「ランチ営業」です。
個人的にはクレープなどの軽食ではなく、ボリュームのある昼食として食べられる商品を平日に販売していくほうが儲かりやすいのではないかと思っています。
オフィス街や住宅街、大学のランチ営業で儲けを確保!


移動販売の平日の出店先としては商業施設やスーパー、ドラッグストア、本屋さんなどがありますね。
今後はそれに加えて、オフィス街や住宅街、企業・大学などへの出店も検討してみてください。
「ランチ難民」という言葉に現れる通り、これらの場所はランチとして食べるものを強く求められる場所。
お客さんの購買意欲としてはかなり大きいはずなのでオススメです。
事前注文で販売効率と売上アップを狙う


また可能であれば、事前注文方式も取り入れてみてください。
上の画像はわたしが事前注文を行った年の売上記録です。
3月の「大商総合商業施設の平日出店」では、11:00〜16:00頃までの販売で13,900円の売上にとどまっています・・。
ですがある企業様限定で事前注文を取って販売した日は、概ね3万円ほどの売上となりました。
事前注文の日は、朝9:00ごろから生地を焼き始めて注文の商品を調理。
その後13:00ごろにはクレープをすべて販売し終えていますので、出店時間としては4時間ほどです。
平日4時間の出店で3万円の売上ですので、十分な儲けといえるでしょう。
「企業のランチタイムに食べてもらうクレープ」として販売してみたのですが、意外にもニーズが高く、多くの方が注文してくださいました。
また事前注文のシステムを取り入れることで、
- 無駄な仕込みがないため、食材の廃棄ロスがない
- 大幅な出店時間の短縮
という大きなメリットも生まれました。
平日の出店でもやり方次第でしっかりと儲けを出すことは可能ですので、このような方法も取り入れることを検討してみてください。
事前注文ってどうやるの?
わたしの場合、事前注文は具体的には以下のような流れ↓で注文から販売までを行っていました。
参考までにご紹介しておきます。
事前注文によるクレープ販売の方法
①出店の3日前。会社の担当者さま宛てに「販売メニューと値段」をメール送信。
②メールの内容が、その会社のパソコン掲示板で告知される。
③掲示板を見た購入希望者さんが各自、私のサイト宛てに
- 名前と電話番号
- メニューとその個数
を送信。
④出店前日に注文をすべてとりまとめ、注文の数だけ仕込みをする。
⑤当日現地でクレープを作り、ひとつづつ個包装・冷蔵保存。
⑥お昼休み、取りに来られたお客さんに配布・精算する。
なお、企業様に事前に販売許可をいただく必要があるのは言うまでもありません。
キッチンカーで儲けを出すためには積極的に行動していき、自ら販路を開拓していく力が必要になることはまちがいないでしょう。
キッチンカーで原価率の低いメニューTOP10!
以上、ここまでキッチンカーで儲けを出すためのコツについて解説してきました。
儲かるかどうかは、オーナーの手腕によるところが大きいのですが、じつは商品を何にするのかによっても儲けは変わってきます。
というのも商品によって原価率が違うため、原価率が低く抑えられる商品を選んだほうが結果として利益が出しやすいのです。
そこで!ここからは「テレビ|水曜日のダウンタウン」で公開されていた内容をもとに、原価率の低い食べ物をランキング形式でご紹介していこうと思います。
結論から言いますとランキングの結果は下記の通りです。
1位:わたあめ
2位:かき氷
3位:ベビーカステラ
4位:ピザ
5位:フライドポテト
6位:もんじゃ焼き
7位:ペペロンチーノ
7位:ぎょうざ
9位:イカ焼き
10位:ショートケーキ
このランキングを参考にしつつ、儲けを出しやすいメニューを選ぶのも一つの方法ですね。
では10位から順にみていきましょう。
原価率の低い食べ物10位|ショートケーキ


スポンジケーキは、泡立てた卵の力で、実際に使用した食材の何倍にも膨らみます。
膨らませて作る食べ物というのは実際の見た目以上に安い原価で仕上がり、利益率は高くなります。



原価率の低い食べ物9位|いか焼き


イカ焼きは、販売される場所がお祭りなどのイベントの場となります。
このような場所では価格販売を高めに設定しやすいことから、結果として利益率の高い商品になるというのが番組の解説でした。



原価率の低い食べ物7位|ぎょうざ


*同率7位でペペロンチーノと並びますので、8位ではなく7位と表記です。
移動販売でぎょうざの販売ってどうなの?と思われるかもしれませんが、実際に餃子の露店(屋台販売)を見たことがありますので選択の余地はありますね。



原価率の低い食べ物7位|ペペロンチーノ


ペペロンチーノの場合、パスタ以外にほとんど食材を使わないため原価率がかなり抑えられるとのこと。
パスタの移動販売はあまり聞いたことがありませんが、参考までに^^



原価率の低い食べ物6位|もんじゃ焼き


ペペロンチーノと同様、移動販売のメニューするというのはあまり現実的ではないような気がします。
ですがやはり、粉ものメニューの利益率の高さがうかがえる結果ですね。



原価率の低い食べ物5位|フライドポテト


今は「ロングポテト」が人気で、先日見かけたロングポテトのおみせも終日行列ができるほどの人気ぶりでした。
しかも利益率が高いとなると、ますます気になるメニューですね。



原価率の低い食べ物4位|ピザ


ここで紹介されていた内容は、「宅配という付加価値」をつけて価格を高く設定できる結果、原価率が安く抑えられるとのこと。
移動販売なら高めの値段設定をしても売れるでしょうから、どちらにしても利益を得やすい商品だと言えそうです。



原価率の低い食べ物3位|ベビーカステラ


ベビーカステラはベーキングパウダーを入れて、膨らませて調理する粉ものメニューです。
前述した通り、膨らませて作るメニューはやはり原価率も低いですね。



原価率の低い食べ物2位|かき氷


かき氷は氷に蜜をかけるだけで出来上がりますので、原価率としてはかなり低く抑えられます。
移動販売でも取り扱っている店舗は多いので、差別化をする工夫も必要になると思います。



原価率の低い食べ物1位|わたあめ


綿あめの原価は「砂糖」のみ。原価はほとんどかかりません。
移動販売では主力商品として扱える商品ではないので、サイドメニューの一つとして考えるといいかもしれませんね。



まとめ
以上、「キッチンカーの儲け」について深堀りしてみました。
おさらいしておくと、儲けを出すコツは下記の5つ。
- 日々の販売記録を残すこと
- 販売収支から儲からない原因を突き止める
- 安売りをしないこと
- 食材の廃棄ロスを出さない工夫をする
- 平日のランチ営業や事前注文を取り入れる
儲けを出しやすいメニューのランキング結果はこちら↓となります。
1位:わたあめ
2位:かき氷
3位:ベビーカステラ
4位:ピザ
5位:フライドポテト
6位:もんじゃ焼き
7位:ペペロンチーノ
7位:ぎょうざ
9位:イカ焼き
10位:ショートケーキ
実際のところはご自身で出店経験を重ね、「売れる出店場所」「売れる商品」を築き上げていくことが重要になるでしょう。
キッチンカーといえど、簡単に儲かるなどという甘い世界ではありません。
「一発逆転大儲け!」ではなく「いかに長く生き残るか」を考えた地道な開業をされたほうが成功しやすいのではないでしょうか。


なお、キッチンカーで成功するためのポイントについてはこちらの記事↑で詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてくださいね。
それではまた☆





